30日間無料!いつでも解約できます!
本記事は「休む」ということについて考えてみます。
著者は、日本リカバリー協会の代表理事・片野秀樹さん。
リカバリーウェアを初めて開発したベネクスの役員でもあり、医学博士でもあります。
片野さんの著書『休養学』は大人気。
発行部数は10万部を突破し、Amazonレビューも300件近く寄せられています。
日本人は「疲労大国」と呼ばれるほど疲れています。
通勤電車で居眠りしている人は珍しくありません。
実際、あるデータでは日本人の約8割が疲れを感じているそうです。
また6時間未満の睡眠しか取れない人も4割ほど。
そんな状況だからこそ、休むことの本当の意味を学ぶ必要があります。
休む=寝る、だけじゃない

片野さんは、まず「休む」イコール「寝る」だけではないと強調します。
もちろん睡眠は大事。
でも「1ヶ月ずっと寝る」ような極端なことをすると、筋力が半減して逆に疲れやすくなってしまうのです。
無理に長時間眠り続けても、体力は落ちる一方。
だからこそ、睡眠プラスそれ以外の休養も必要になるといいます。
疲労と疲労感は別物
「疲れがたまる」「疲れをとる」など、私たちはよく言います。
しかし日本疲労学会の定義では、「疲労=活動能力が低下している状態」とされています。
そこに伴う不快感が疲労感。
本来、動物は疲労感を覚えたら動かずに回復を待ちます。
でも人間は、甘いもので誤魔化すなど「マスキング」をしながら活動を続けることが多い。
これが問題だと片野さんは警鐘を鳴らします。
疲労を放置したまま無理をしていると、やがて体のバランスが崩れ、病気のリスクも高まるからです。
休養にもさまざまな種類がある
一般的には「健康づくりの3要素=運動・栄養・休養」といわれます。
でも私たちは学校で運動や栄養は習っても、休養はほとんど学びません。
そのため「休む=寝る」と思い込みがちです。
しかし、片野さんの提唱する『休養学』では、休養を大きく生理的休養・心理的休養・社会的休養の3カテゴリーに分かれます。
さらにそれを7つのタイプに分類し、必要に応じて組み合わせるのが効果的です。
【生理的休養】
- 休息タイプ
- いわゆる「睡眠」「昼寝」「何もしない時間」
- 体が“静かに休む”ことで回復を図る
- 運動タイプ
- ウォーキングやストレッチなど軽い運動で血流を改善
- 入浴なども血行促進に役立ち、疲労回復へつながる
- 栄養タイプ
- 胃腸を整え、食事からのエネルギー吸収を高める
- 空腹の時間を設けたり白湯を飲んで体を温めることも効果的
【心理的休養】
- 親交タイプ
- 人、動物、自然などに触れ合い、ストレスを軽減
- 信頼できる仲間や家族と過ごす時間
- 娯楽タイプ
- 音楽・映画・ゲームなど、自分の好きな活動を短時間でも楽しむ
- ただし「長時間打ち込みすぎ」で逆に疲れないよう注意
- 造形・想像タイプ
- 何かを“創る”“空想する”ことでストレスから意識を切り離す
- 絵を描く、DIY、料理、俳句、妄想などもOK
【社会的休養】
- 転換タイプ
- 環境や視覚的な刺激を変えてリフレッシュ
- 部屋の模様替え、通勤ルート変更、旅行、ファッションチェンジなど
複数の休養を同時に取り入れる
これら7タイプを組み合わせると、相乗効果が得られます。
たとえば家でスープを作る場合。
「栄養タイプ」で胃腸をいたわり、さらに調理が好きなら「娯楽タイプ」や「造形タイプ」にもなる。
誰かと一緒に作れば「親交タイプ」。
公園まで運んで飲めば、散歩で「運動タイプ+転換タイプ+自然との進行」まで同時に満たせます。
こうして一度に複数の休養を取ると、とても効率的。
オンよりもオフを先に考える「オフファースト」の発想
日本人の多くは朝から既に疲れています。
原因の一つは「お疲れ様文化」。
疲れていることが当たり前、むしろ美徳のようになっている。
でも、活動能力が下がっている状態で仕事をしてもパフォーマンスを発揮できません。
スポーツの世界で知られる「フィットネス疲労理論」は、「体力-疲労=発揮できるパフォーマンス」と示します。
つまり、疲労がゼロに近いほど本来の力を発揮できる。
にもかかわらず、多くの人は疲れが残った状態で働いているのです。
そこで大事なのが「オフファースト」という考え方。
まず休みをしっかり計画し、そこから逆算して仕事に臨むのです。
とくに「勤務間インターバル」という概念が欧州にはあります。
仕事が終わってから次の仕事が始まるまで、最低でも11時間空けなさいという法律です。
日本では義務化されていませんが、この時間をどう過ごすかで疲労回復は大きく左右されます。
オフをマネジメントする重要性
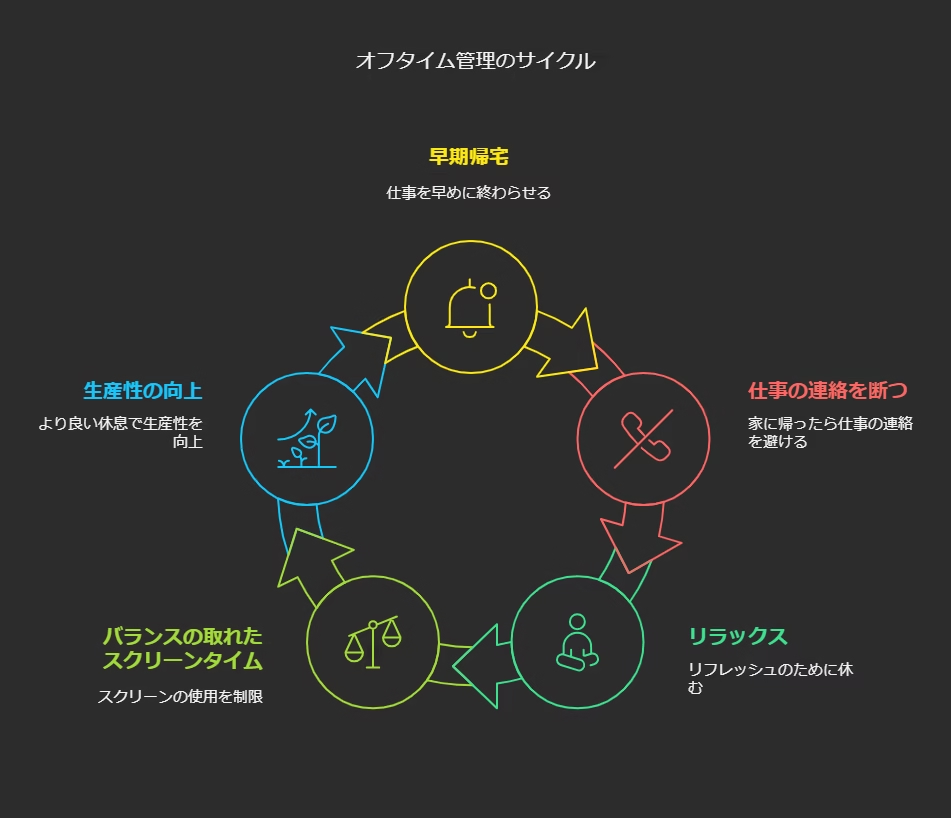
多くの日本企業は、働き方改革で残業を減らしています。
しかし、家に持ち帰って仕事をする、スマホで仕事のメールをチェックするなど、「見えない残業」が増えている現実があります。
せっかく早く帰っても、オフの時間を仕事に奪われていれば休めません。
疲労を回復できないまま翌日を迎えれば、生産性も低下します。
だからこそ、オフの時間こそマネジメントが必要。
自宅に着いたらなるべく仕事の連絡を断ち、一気に休む。
SNSやメールチェックもメリハリをつけて、休養を最優先にしましょう。
まとめ
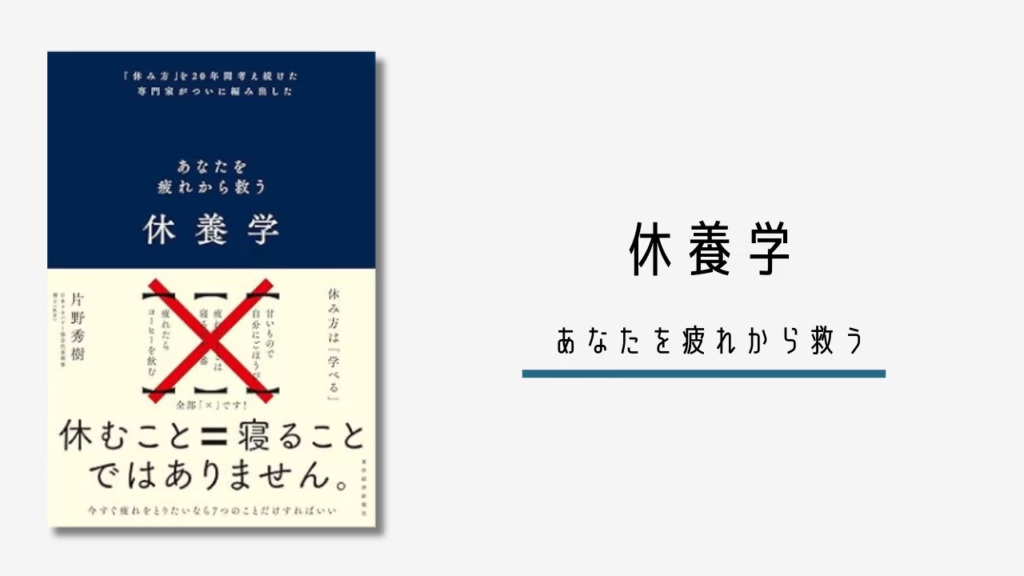
- 休む=寝る、だけではない。
- 疲労と疲労感は別。マスキングに注意。
- 7タイプの休養を組み合わせ、積極的に休む。
- オフを管理し、疲れを翌日に持ち越さない。
お疲れ様という習慣は、一見やさしそうに聞こえます。
しかし、それが当たり前になると、自分も他人も「疲れたまま働くのが当然」になってしまう。
大事なのは、疲れない体を手に入れること。
そして元気に働き、余裕をもって人生を楽しむことです。
片野さんいわく、「休みは攻めるもの」。
主体的に、計画的に休養を取ることで、心も体も回復します。
翌朝にパッと目が覚めて、やる気と活力がみなぎる状態。
そんな日々を実現するために、ぜひ「オフファースト」の発想を取り入れてみてください。
休むことをネガティブに捉えず、むしろ積極的に取りに行く。
そうすることで、あなたのパフォーマンスはきっと上がります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

30日間無料!いつでも解約できます!
「そもそもAudibleについてあまり詳しく知らない」
と思った方は以下の記事を参考にしてみてください!【2025年最新版】オーディブル(無料体験)の始め方:完全ガイド
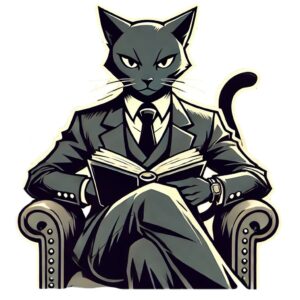
約40万作品のうち12万作品が今なら1か月間無料で聴けます!
家事や通勤・通学中に”ながら聴き”ができるのでおすすめです!
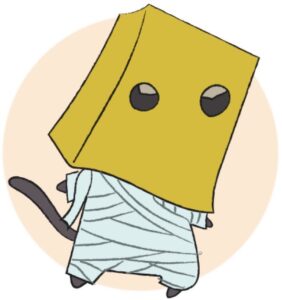
この記事が役立ったら、ぜひコメントやシェアをお願いします!
次回も役立つ情報をお届けしますので、お楽しみに!
